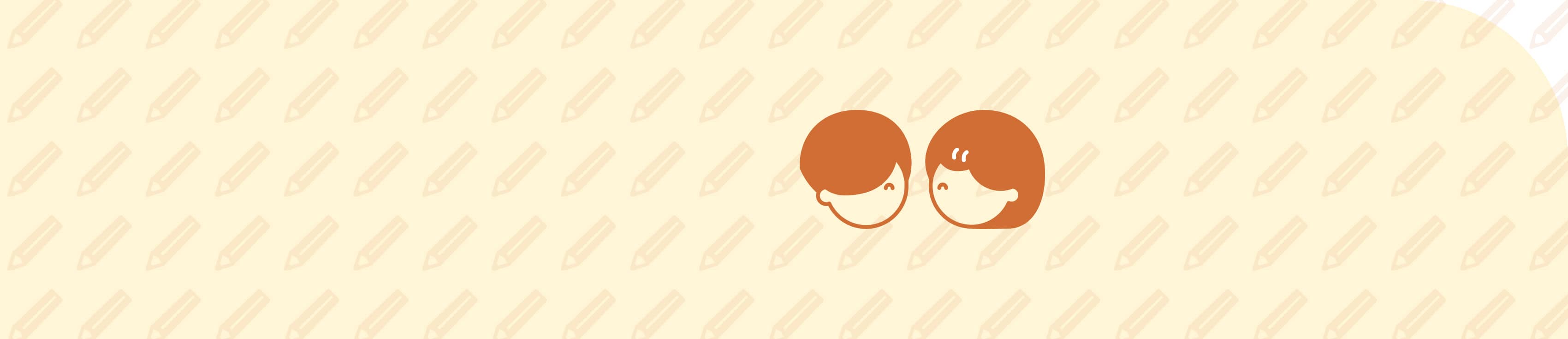

気管支喘息
Explanation解説

気管支などの空気の通り道が炎症を起こして、狭く、通りにくくなることで、咳や息苦しさが出る病気です。ほこりやタバコ、ストレスなど色々な刺激が原因になるといわれています。咳やたん、ゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸音がするといった症状があらわれ、夜間や早朝に起こりやすいのが大きな特徴です。その他にも、季節の変わり目など気温差が大きい時や、かぜなどの感染症にかかった時、またその後に症状がでやすい傾向があります。ぜんそくを予防するためには、十分な睡眠をとること、ストレスをためないようにすること、タバコの煙があるところは避けること、などが重要です。
ぜんそくの診断や、ぜんそくの状態を確認するために、呼吸機能検査(スパイロメトリー)を行います。まず息を思い切り吸い込み、次に力いっぱい吐いていただきます。その時の肺活量や、最初の1秒間で吐き出した空気の量(1秒量)、息の速さの最大値(ピークフロー)などを測定します。
ぜんそくの方の気道には、慢性的な炎症が起きており、症状がない時でも気道の炎症は続いています。この状態を放っておくと、気道の粘膜に変化が起こり、気道が狭くなったまま戻らなくなってしまい、悪化してしまいます。そのため、ぜんそくの治療は発作時だけでなく、症状が起こらないように毎日、吸入薬を中心とした薬物療法を続けていくことが重要です。最初にしっかり治療を行い、症状を確認しながら年単位で徐々に薬を減らしていき、「寛解」という薬物療法を行わないで過ごすことができる状態を目指します。


